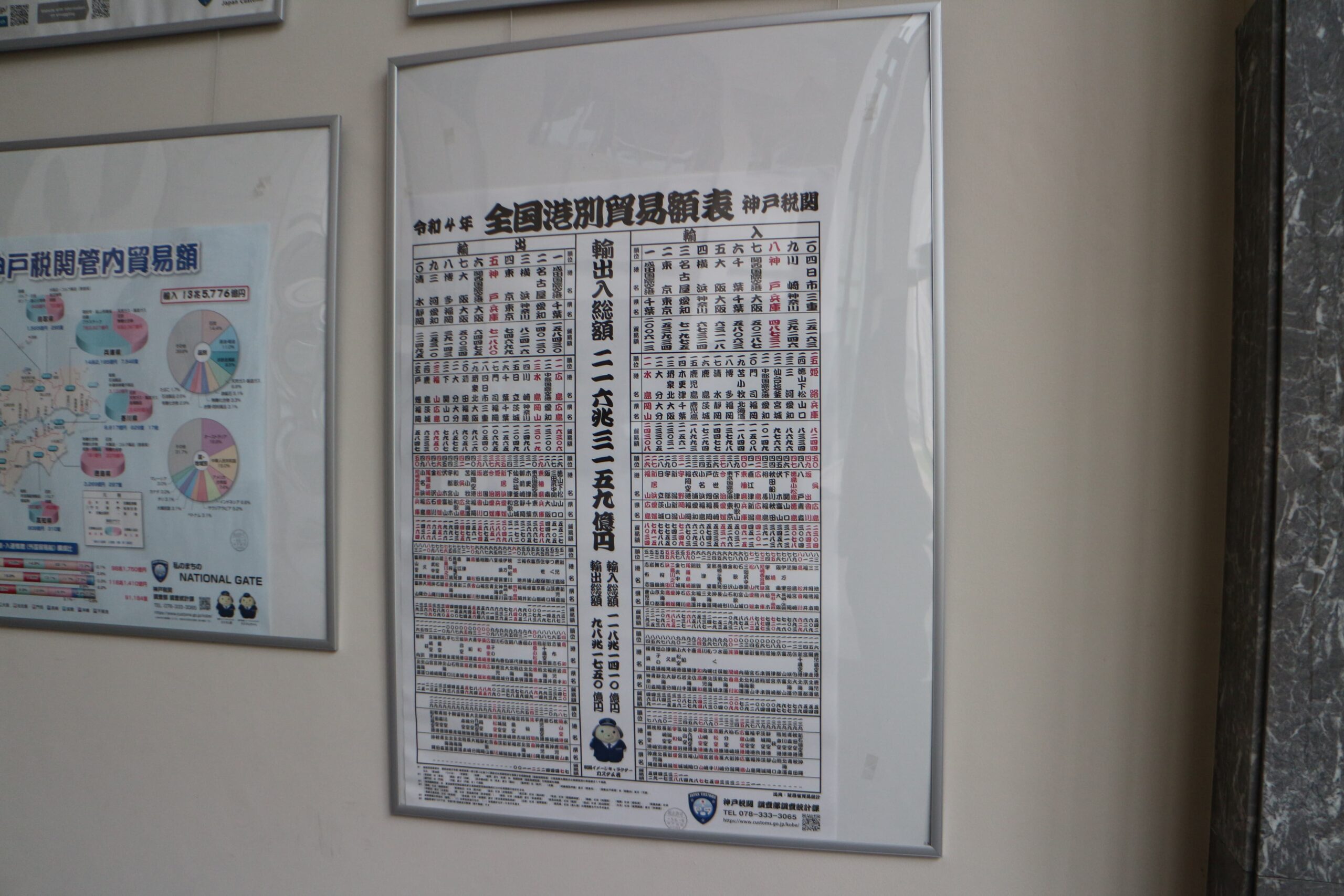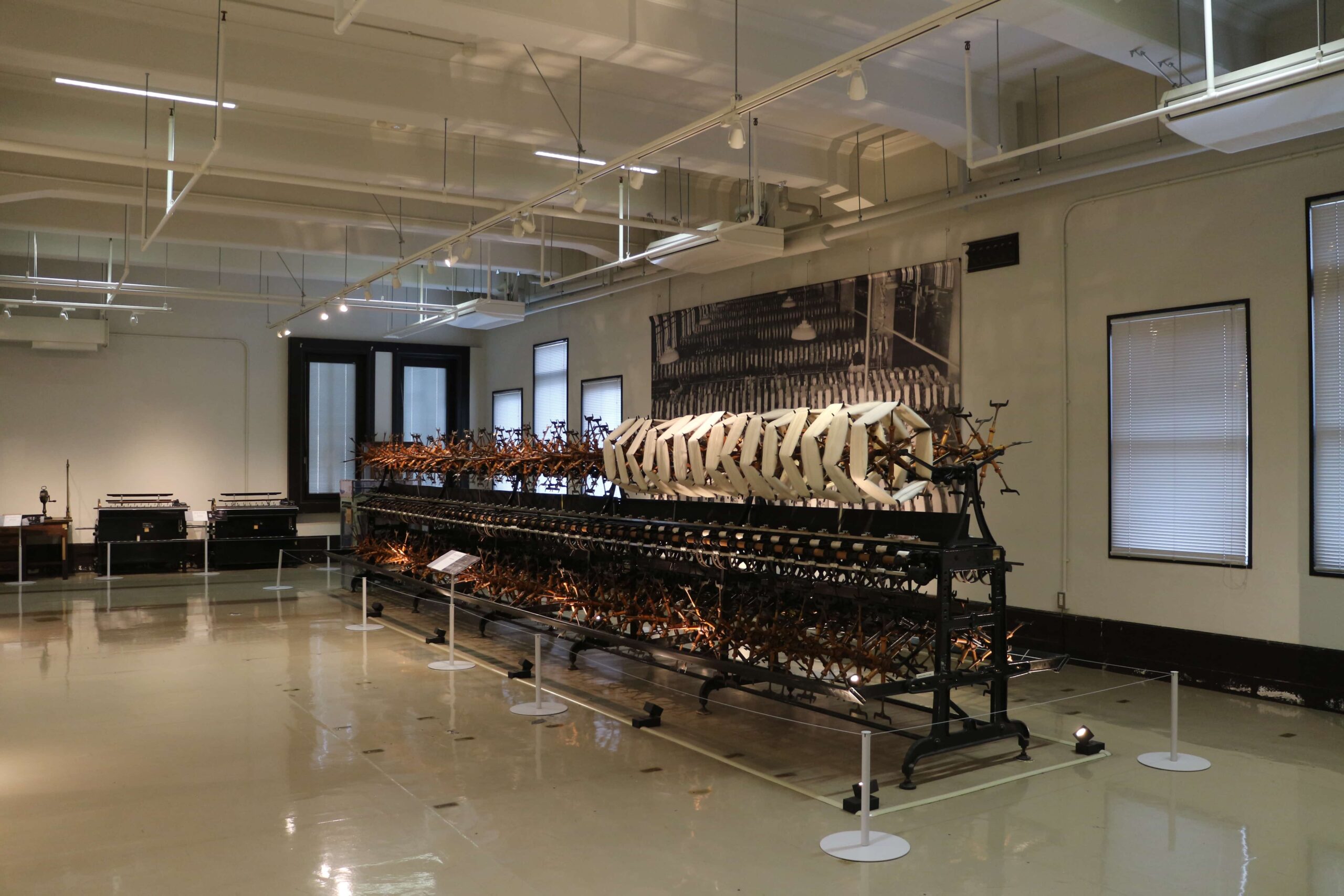こんにちは、山陽沿線歴史部の内膳正です。
前回に続いて垂水を歩いてみたいと思います。

垂水駅前のビル「レバンテ垂水1番館」の地下にある垂水日向遺跡展示コーナーには縄文人のものとされる足跡が展示されていました。レバンテの建設時の発掘調査で、この辺りからは砂浜を歩いた縄文人の足跡が多数見つかったそうです。

「レバンテ垂水1番館」の西側では市場や商店の建ち並んでいたエリアが垂水中央東地区再開発事業として工事中です。
垂水日向遺跡は昭和63(1988)年より長年に渡って調査が続けられていて、つい最近工事が始まったこの地区でも発掘調査が行われました。やや内陸に入ったこちらでは時代が少し下った奈良時代から平安時代にかけての遺構が見つかっています。ここ垂水は奈良時代から平安時代の末頃にかけて、奈良・東大寺の荘園で「垂水荘」と呼ばれていました。発掘調査では当時のものとされる建物の遺構や硯を始めとする遺物が見つかり、一時一般公開されていました。

山陽電車とJRの高架を潜って浜側へ出てみました。JR垂水駅のすぐ浜側にあるのが海神社です。

海神社ははるか古代、神功皇后が社殿を建立したことに由来するという伝説が伝わる古社です。伝説にももちろん興味深いものがありますが、これまで垂水の遺跡を歩いてから訪ねると、海の幸に恵まれて古くから人々の営みがあったこの地に海の神をまつる神社が自然と建立されたのではないか。そんな気もしてきました。

海神社から海側を眺めてみます。鳥居の向こう、漁協の建物越しに大阪湾を眺めることができました。青々とした初夏の海沿いを少し歩いてから、垂水を後にすることにしました。