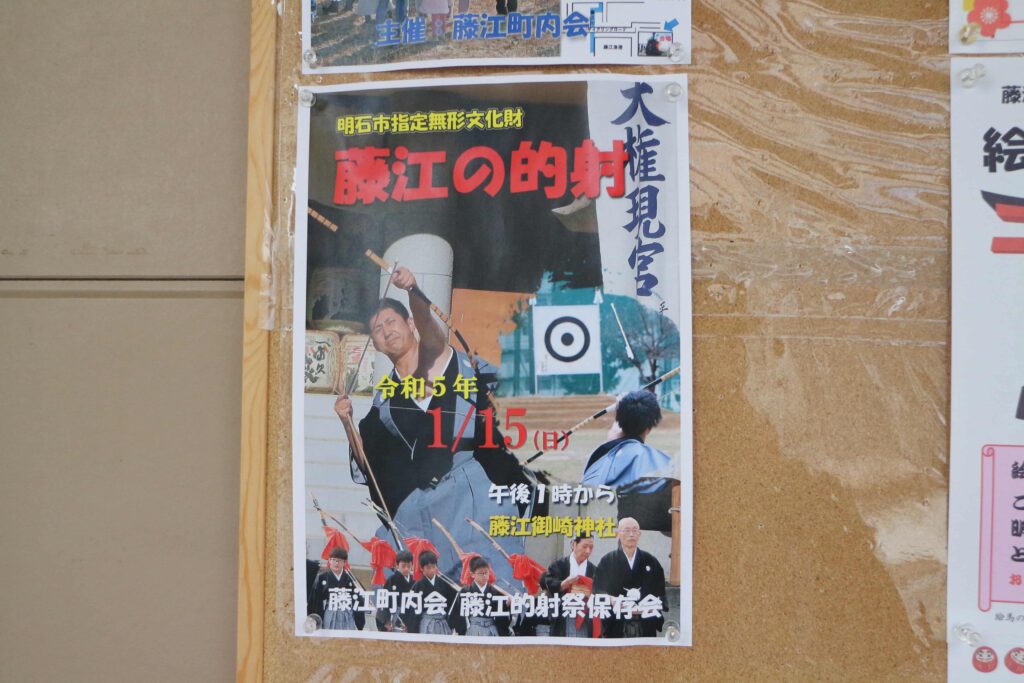こんにちは、山陽沿線歴史部の内膳正です。
前回に続いて、明石を歩いてみたいと思います。

入り江状になった明石港の西側を歩いてみることにしました。この辺りの地名は材木町です。明石城の築城の際に港に近いこの辺りに材木商が集められたことが由来だそうです。
現在のような明石の街が整備されたのは江戸時代の初めの元和3(1617)年に明石藩が設置されてからのことです。初代藩主となった小笠原忠政(忠真)は当初は西新町駅近くの船上城に入城しましたが、当時の将軍・徳川秀忠の命で現在の位置に明石城を築城し、城下町の整備を始めました。当時の城下町は東側に町人や職人の町、中央部には商人の町、そして、西部には廻船問屋や船大工の集まる港湾関係者の街に大きく分けられていました。この時、中央部に設けられた商人町では明石で水揚げされる海産物や加工品が取引されて大変にぎわった町となり、後に前回訪ねた魚の棚商店街へと発展していくことになります。

材木町の一角に大きな神社がありました。こちらは岩屋神社です。

岩屋神社ははるか神代の成務天皇13年(143)年に対岸の淡路島の岩屋から遷ったのが始まりと言われ、非常に長い歴史をもっています。そのせいか、境内もどこか趣のある雰囲気ですね。淡路島から遷ったという伝説に因んで、毎年7月には海に船を出す「おしゃたか舟神事」が執り行われています。古くから港湾関係者の多いこの辺りの地区では航海の安全を願う神社として古くから信仰されていたようですね。

住宅地を通り抜けて港の先端に着きました。岬のように飛び出した護岸には石造りの灯台が佇んでいます。こちらは旧波門崎燈籠堂で、江戸時代に作られた灯台です。現在に残る燈籠堂は江戸時代の初め頃に設けられたもので、以来、明石港を出入りする船の目印としての役割を果たしてきました。戦後の昭和38(1963)年に新しい灯台が建設され、この燈籠堂は役目を終えましたが、今もこの地で明石港を見守っています。

燈籠堂から明石港を眺めてみました。ビルに囲まれた港を、ちょうど淡路島へ向かう高速船が出港していきます。明石は間もなく春本番を迎えます。明石海峡で水揚げされた様々な海産物で魚の棚が賑やかになるまでもうすぐですね。
淡路島への船が大橋をくぐって見えなくなるまで見送ってから、明石港を後にすることにしました。